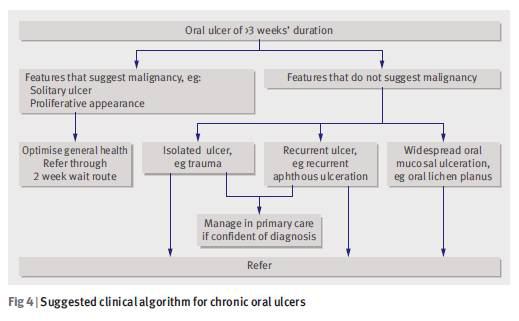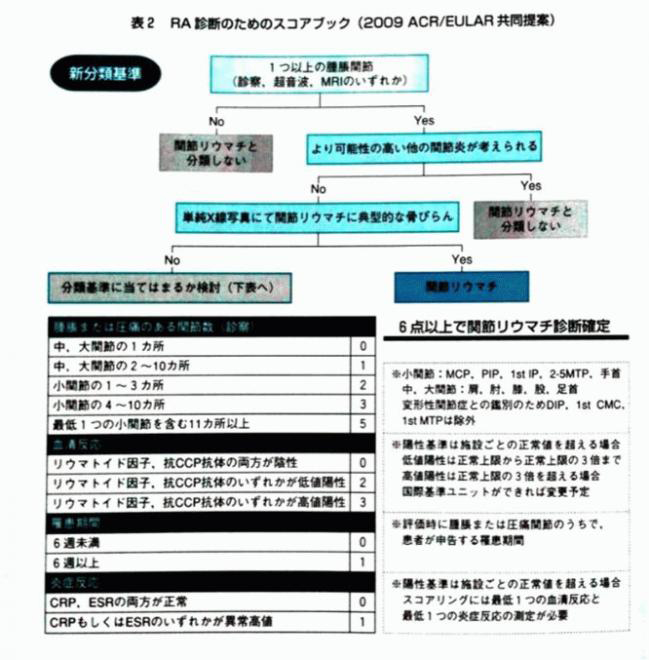【文献】
Initial treatment of depression in adults。UpToDate ONLINE18.1
【要約】
総論
抗うつ薬の試験の文献を評価するときには、Publication biasを考慮しなければならない。(政府または独立したスポンサーがわずかで、製薬会社と出所不明が多い。)
薬の選択
・ほとんどのシステマティックレビューにおいて結論づけられていることには、臨床的にもQOLにおいても、治療コストについても、特定の抗うつ薬のなかで、どれを特別選ぶべきかということはない。
・何の薬を使うかということよりも、患者が受け入れられる薬を使って治療することと、症状を寛解させるのに十分な容量を使用するということのほうが、重要である。
・SSRIsがプライマリケアではしばしば第一選択として使われている理由としては、副作用が少なく、過量投与でも、危険が少ない点である。
the American College of Physicians (ACP)からの2008年臨床診療ガイドラインでは、以下の12の第二世代抗うつ薬から治療を開始することを強く勧めている。
ブプロピオンbupropion(NDRI;ウェルブトリン) 国内未
シタロプラムcitalopram(SSRI;セレクサ) 国内未
デュロキセチンduloxetine(SNRI;新☆サインバルタカプセル)
*一日一回投与のセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬
エシタロプラムescitalopram(SSRI;レクサプロ) 国内未
フルオキセチン fluoxetine(SSRI;プロザック) 国内未
フルボキサミンfluvoxamine(SSRI;デプロメール、ルボックス)
ミルタザピン mirtazapine (NaSSa;新☆レメロン、リフレックス)
*ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬
ネファゾドンnefazodone(SNRI;サーゾーン) 国内未
パロキセチンparoxetine(SSRI;パキシル)
セルトラリン sertraline(SSRI;ジェイゾロフト)
トラゾドンtrazodone(SARI;デジレル,レスリン)
ヴェンラファキシン venlafaxine(SNRI;エフェクサー) 国内未
☆ネファゾドンnefazodone(SNRI;サーゾーン)には肝細胞毒性あり
・過去に受け入れの良い薬で治療に成功した患者は、うつ病が再発した際には、同じ薬を再開すべきである。
・薬の選択の際には、臨床医の使いやすさ(慣れ具合)、価格、好みと副作用を考慮すべきである。
副作用
・第二世代を評価した203の試験のシステマティックレビューではmirtazapine and paroxetineが他の第二世代抗うつ薬に比べて、体重増加がおこりやすい。
・ うつ病自体が、糖尿病を進展させるリスク要因である。65歳以上の1000人を10年追跡した前向き研究では、うつ病の人は、抗うつ薬による治療に関わら ず、うつ病を持たない人に比べて2倍以上糖尿病に罹患する率が高かった。(hazard ratio 2.3, 95% CI 1.3-4.1)
・ ケースコントロール試験において、うつがあり、糖尿病がないおよそ166,000人の患者のうち、抗うつ薬の中等量~高用量の長期間(2年以上)の使用 が、顕著に糖尿病のリスク増に関係した。(incidence rate ratio 1.8, 95% CI 1.4-2.5)
糖尿病のリスク 増加の見積もりは、amitriptyline (incidence rate ratio: 1.43, 1.03-1.98), fluvoxamine (incidence rate ratio: 4.91, 1.05-23.03), paroxetine (incidence rate ratio: 1.33, 1.02-1.73), and venlafaxine (incidence rate ratio: 2.03, 1.18-3.48)
・他の副作用については一般的な内容であったので割愛。
用量
・少量から開始することで、抗うつ薬の副作用を最小限にすることができる。
・一週間ごとに最大量まで漸増する。
・薬はたいてい朝に内服する。内服後、8時間から12時間は穏やかな興奮作用があり、眠りを阻害する可能性がある。
・SSRIは、寛解を達成するためには典型量より高用量を必要とする。
・三環形抗うつ薬は、より少量でも高容量と同程度に効果があるようす。
フォローアップ
・治療開始から治療に反応するまでの時間は2週間から6週間と考えられている。
・ある試験では治療開始から2週間以内の早い反応は、治療の安定した効果と寛解の継続を予測させる。
・2週間過ぎても反応がない場合、薬の量を増量しなければならない。
・最大量で8~10週間経過しても反応がない場合は、異なる抗うつ薬(同じまたは異なったクラスの)を試すか、精神科に紹介しなければならない。
・部分的な反応の場合は、bupropion(国内未) or buspirone(国内未)を追加するか、患者が薬の追加を好まなければ、他のSSRI、SNRIに換える。
治療期間
・抗うつ薬は一般的に、最初のうつのエピソード後、最短でも6-9ヶ月内服しなければならない。
・患者による薬の中断は多い。
・再発も多い。特に3回以上繰り返している例は薬の継続が望ましい。
精神科へ紹介するケース
・ファーストラインの薬を患者が受け入れられない、または効果がない場合
・思考障害を伴った重症なうつか、自殺衝動がある場合
・薬品中毒や精神依存、薬物乱用を伴っている場合
・患者が認知行動療法を強く望んでいる場合
【日付】
2010年7月14日(水)