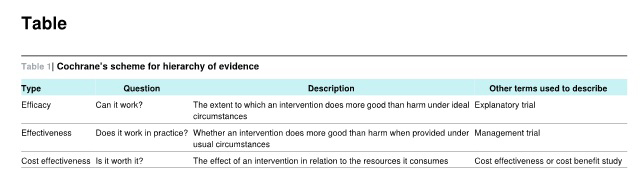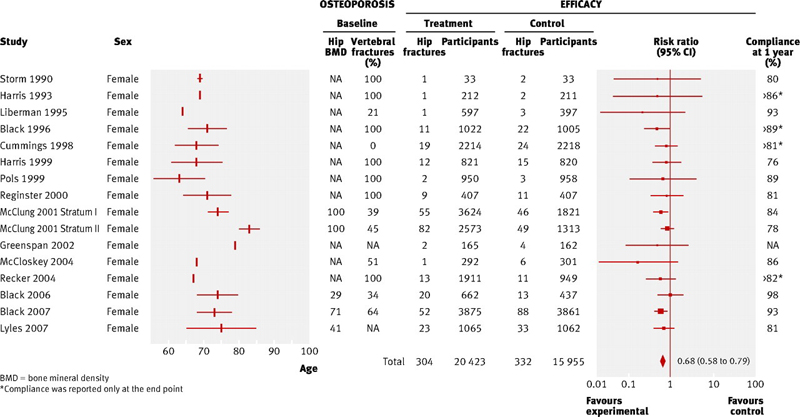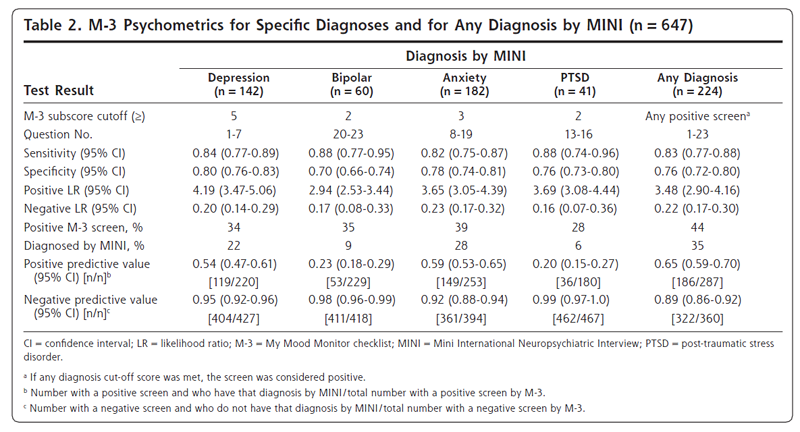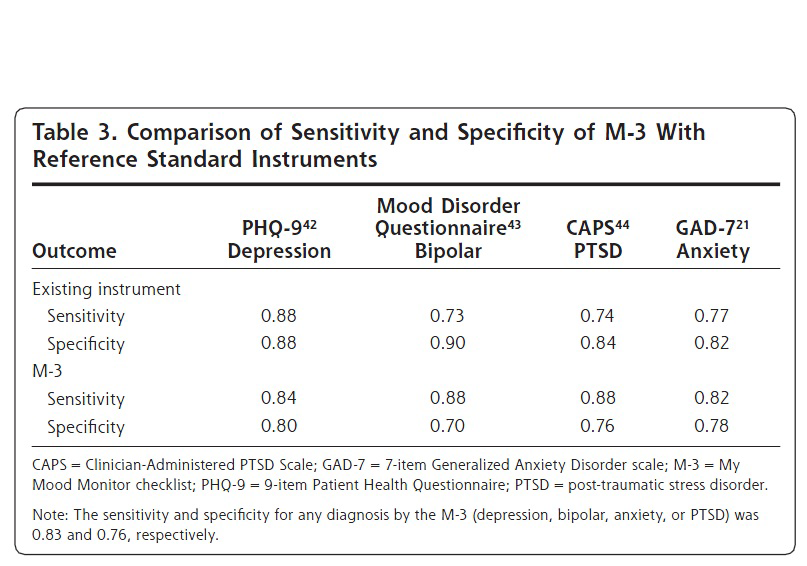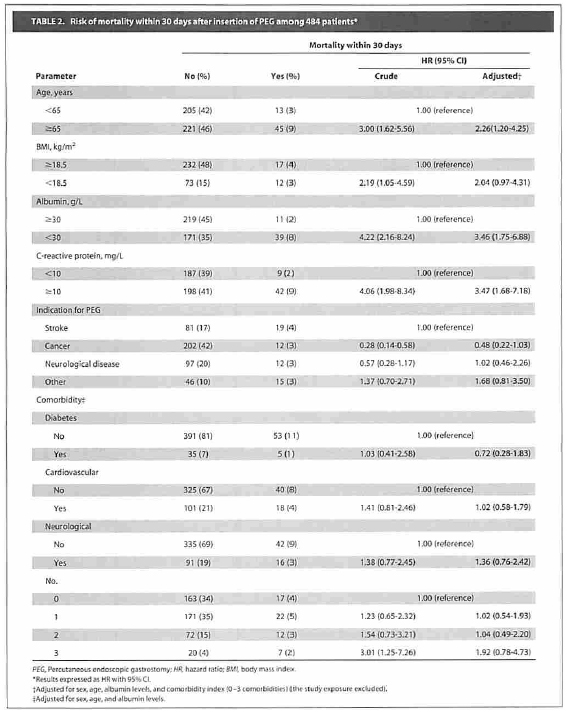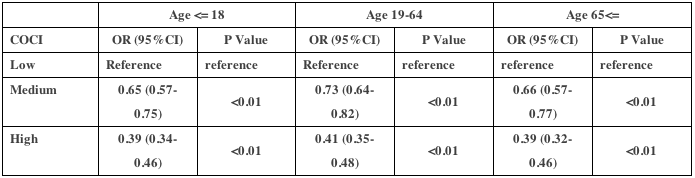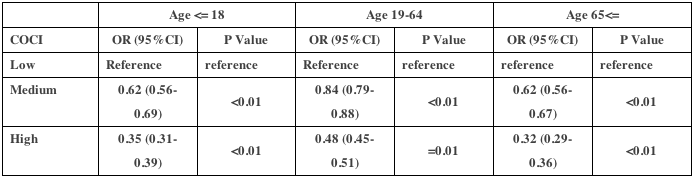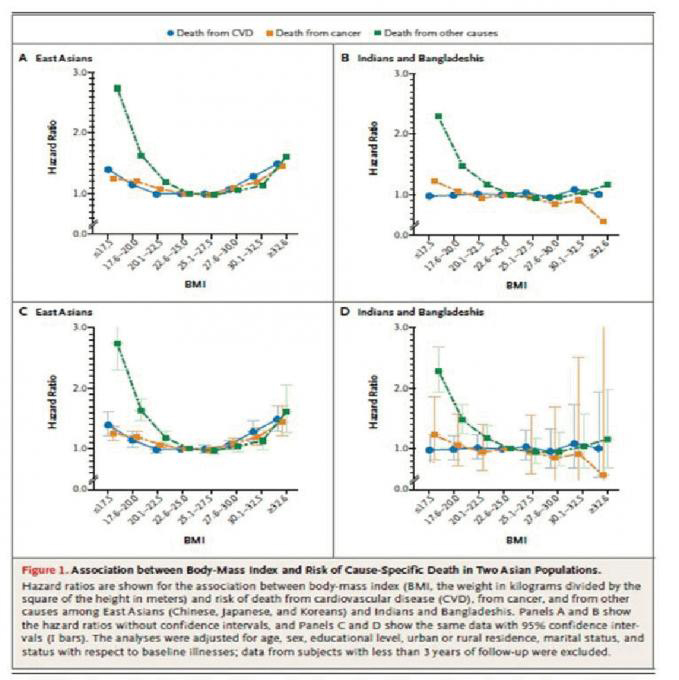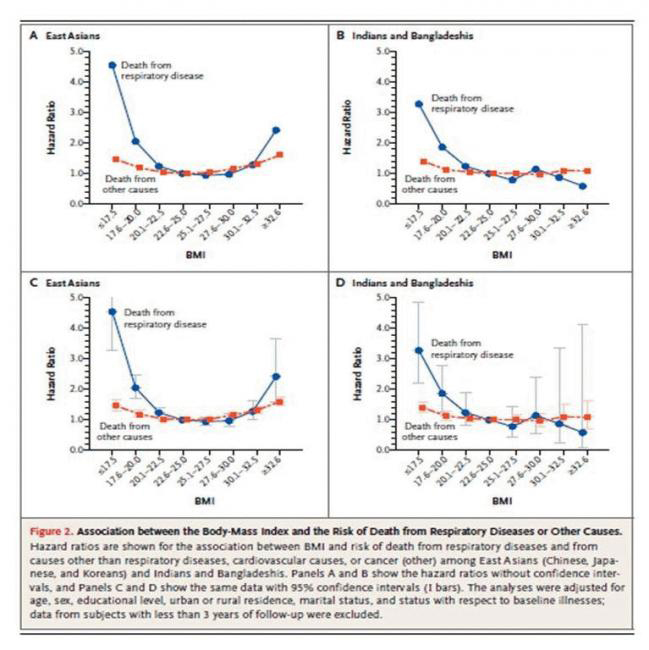【文献名】
枝廣淳子・小田理一郎.もっと使いこなす!「システム思考」教本.東洋経済新報社.2010
【要約】
<この本の内容>
本書はシステム思考の実践・応用に主眼を置き、序章で視点の変化・メンタルモデルの修正の重要性、Ⅰ章でシステム思考のためのツールの紹介、Ⅱ~V章で個人や組織、事業戦略や社会に関するシステム思考の実践・応用の31事例を紹介している
<共有したい文章>*一部編集しています
視座の高さ・視野の広さ (p2)
「見る視座によって見える範囲も見える要素も、そして関心ある事項がその周囲とどういった関係にあるかも、まったく違ったレベルで考えることができる」
今という時間の意味 (p5)
「今という時は、さまざまな物事の推移の交差点・・・現在は過去の様々な影響の終結する点であり、現在の行動は未来の様々な時点に影響を与える」
全体の視点で見る~全体最適 (p12)
「全体最適は概して望ましいのですが、全体主義に陥ってしまうことには気をつけなくてはいけません」
視点を変えるツールの特徴 (p23)
「全般に共通して、以下のような基本動作を含んでいます
● 現場を徹底的に観察する
●時間軸をのばす
●全般的な流れ、パターンを把握する
●自分の思考や行動を見える化する
●ゆっくりと考える
●見えていなかったものを探す
●前提を見つめ直す
●立場を変えて考える
●立場を超えて考える
●ゆらぎを起こす
●問いかける/探求する
学習する組織のための3つのコアコンピタンス (p37)
「1システム思考による複雑性の理解、2メンタルモデルを克服しダイアログを勧める共創的な会話、3志」
<共有したい事例>
Ⅱ-1 成功のための行動習慣が身につかない (p40)
「行動は構造・環境が作り出す。・・・行動を変えるのではなく環境を変える」
Ⅱ-7 仕事がなかなか終わらない (p61)
「システムを上手く動かすには、『自己組織化』『レジリアンス』『階層化』が重要」
「階層化の本来の目的は全体の貢献をなす下部組織の働きを効果的にすることだが、この目的は組織の上部と下部それぞれで忘れられてしまいがち」
「全体の目的に向けての調整と、それぞれの下部組織の自由度とのバランスをとることで階層化は機能する」
「また、時間の変化と共に環境変化の衝撃を吸収する能力(=レジリアンス)、適応して自らを進化させる能力(自己組織化)を兼ね備えたシステムづくりを心がけましょう」
Ⅲ-2 プロジェクトがどんどん遅れていく (p84)
「問題が発生してから生じるコストは、悪循環の他のさまざまな要素・関係者との調整をともない、とても大きなものとなります。事前の調整や段取りをしっかりすることで、はるかに少ない投資で問題が生じた際の大きなコストを回避することができる。」
Ⅲ-4 問題解決が新たな問題をつくる (p99)
「自分たちも問題構造の一部である」
Ⅳ-2 企業成長の罠 (p124)
「事業の成長よりも先に組織の能力を成長させねばならない。それができないのなら事業の成長を緩める。」
「『速いものが遅く、遅いものが速く』と、複雑なシステムの挙動は合理性を超えています。ジレンマの構造に気づき、自らを律して成長を緩めることができて初めて持続的な成長を実現できる。」
Ⅴ-2 対処しても野良犬だらけ (p156)
「潜在的な環境システムを変えない限り、問題への有効な策は打てない」
Ⅴ-4 U理論によるサステナブル・フード・ラボ (p162)
「いかに自分たちの思いこみや固定観念を捨てて変われるかが最大のチャレンジ」
V-5 目に見えない資本がものをいう (p166)
「経済開発では、自国の経済にある自己強化型ループを強めること、またそういった自己強化型ループを多重に埋め込むことが重要なポイント」
「測りにくいからといって重要でないということはなく、人的資本や社会資本など一見わかりにくいが重要な富の源泉となるものがあり、これらの富を将来に渡って枯渇させず、維持または増加させるマネジメントが重要」
【考察とディスカッション】
視点を変えるツールの共通の基本動作のリストは、実践のコツとして個人レベル、組織レベルで役に立つと思った。また、Bio-psycho-social Approachだけでなく、不確実性に耐えて扱う時もこのシステム思考は、家庭医にとって重要な熟達すべきスキルだと感た。
【開催日】
2011年5月18日