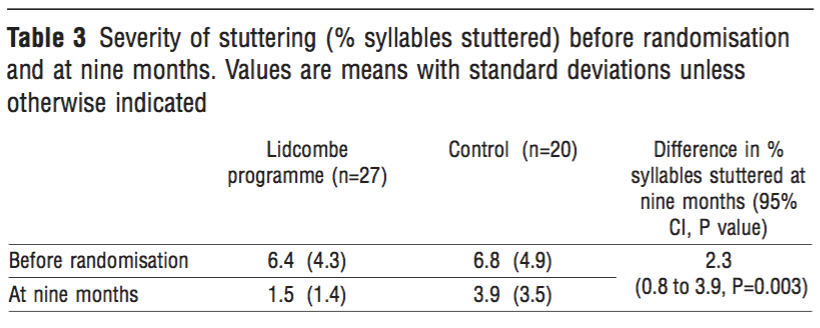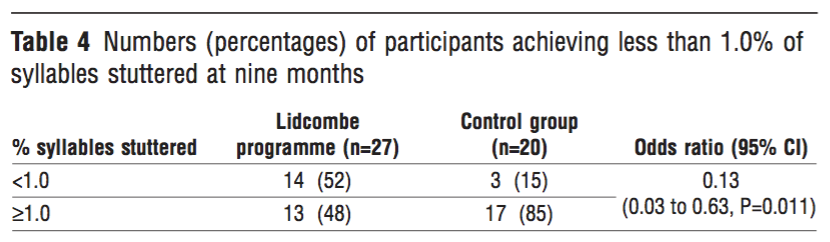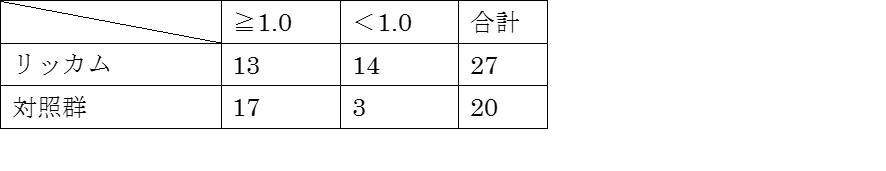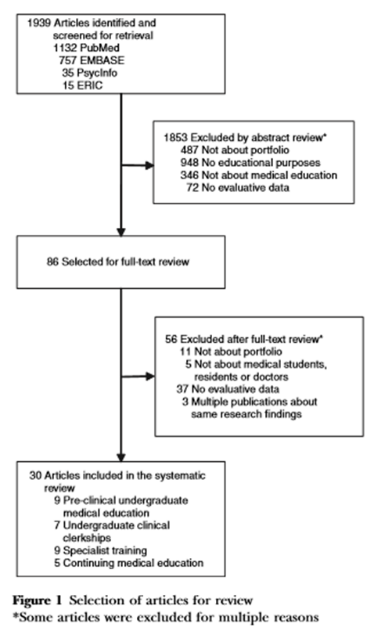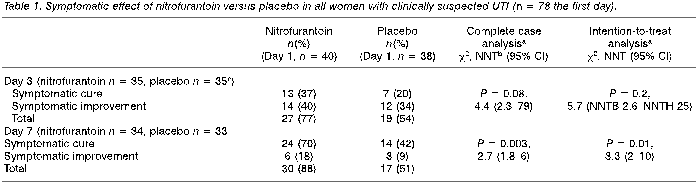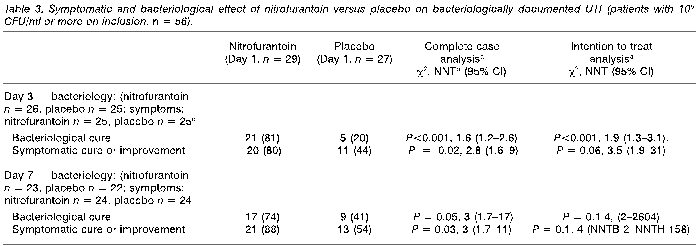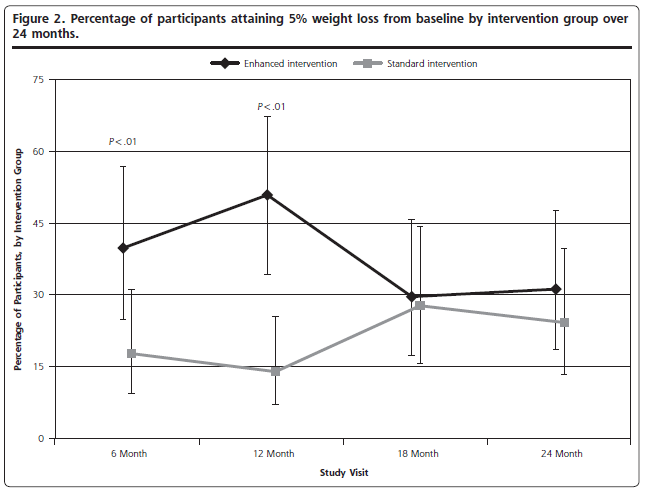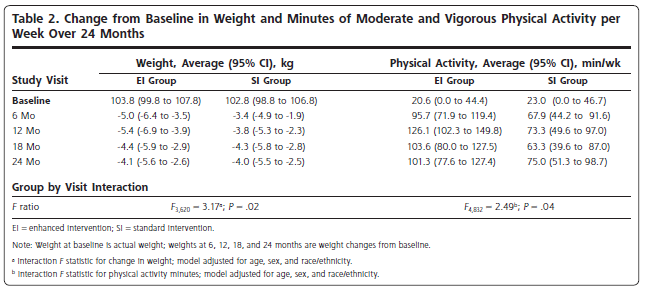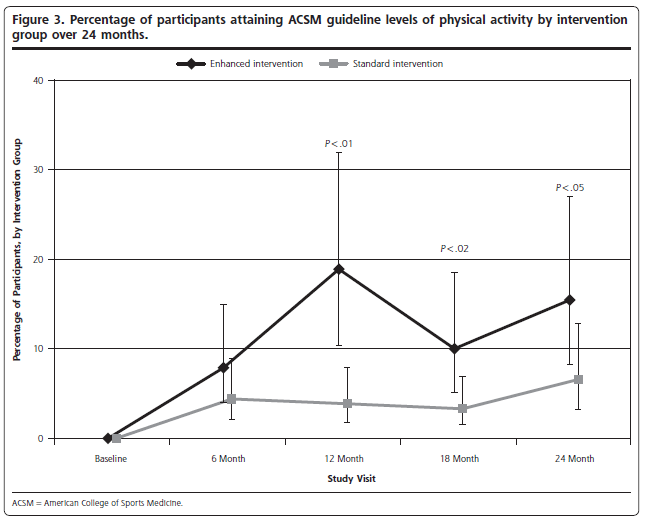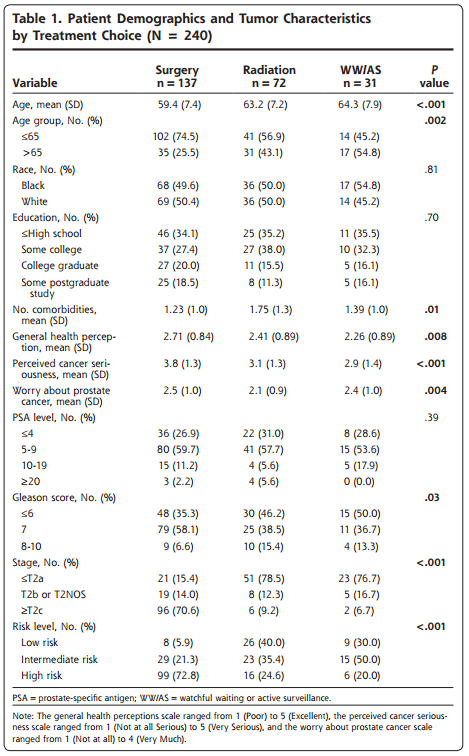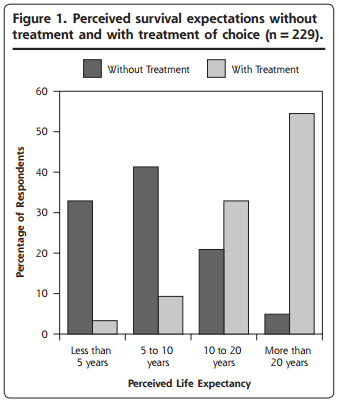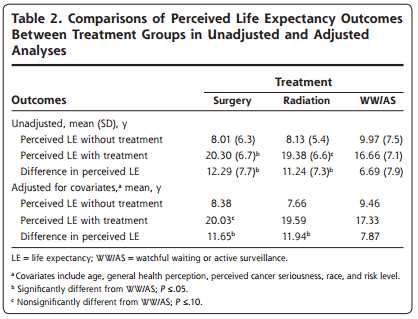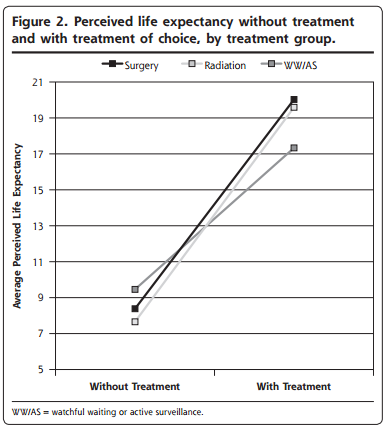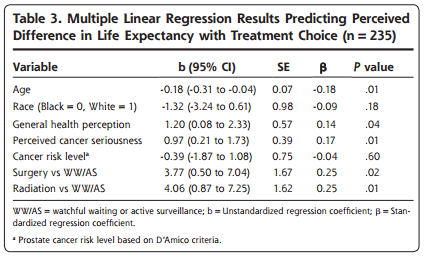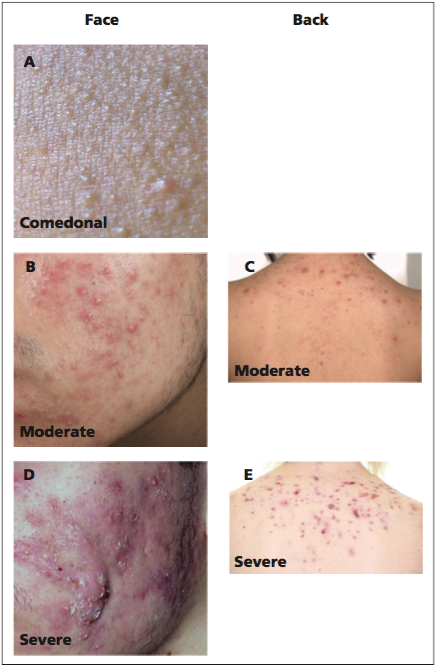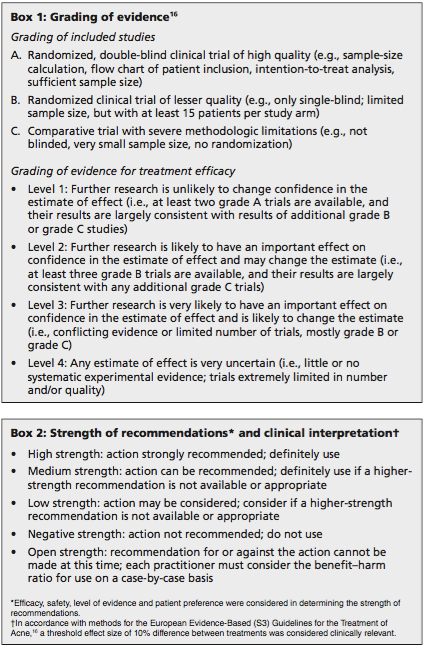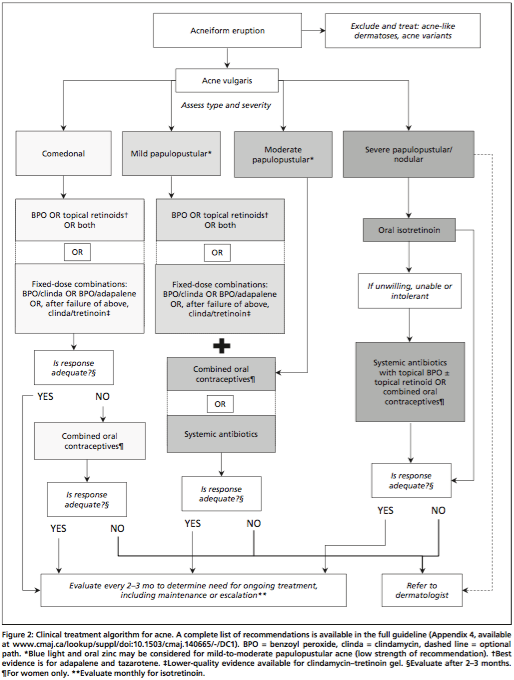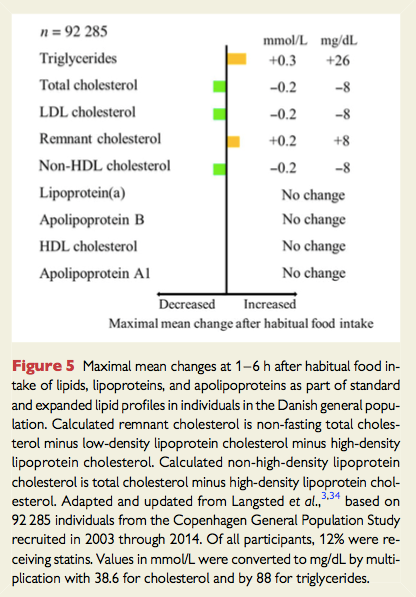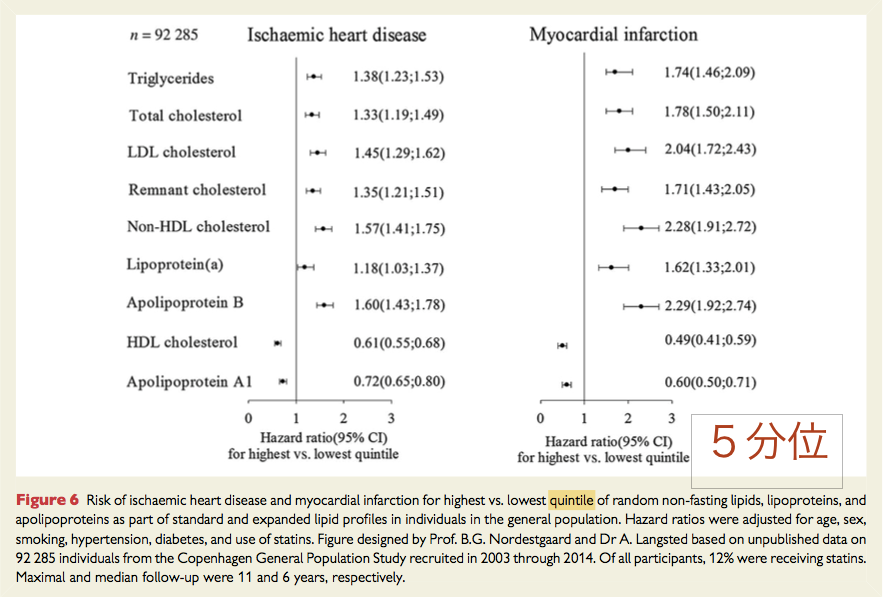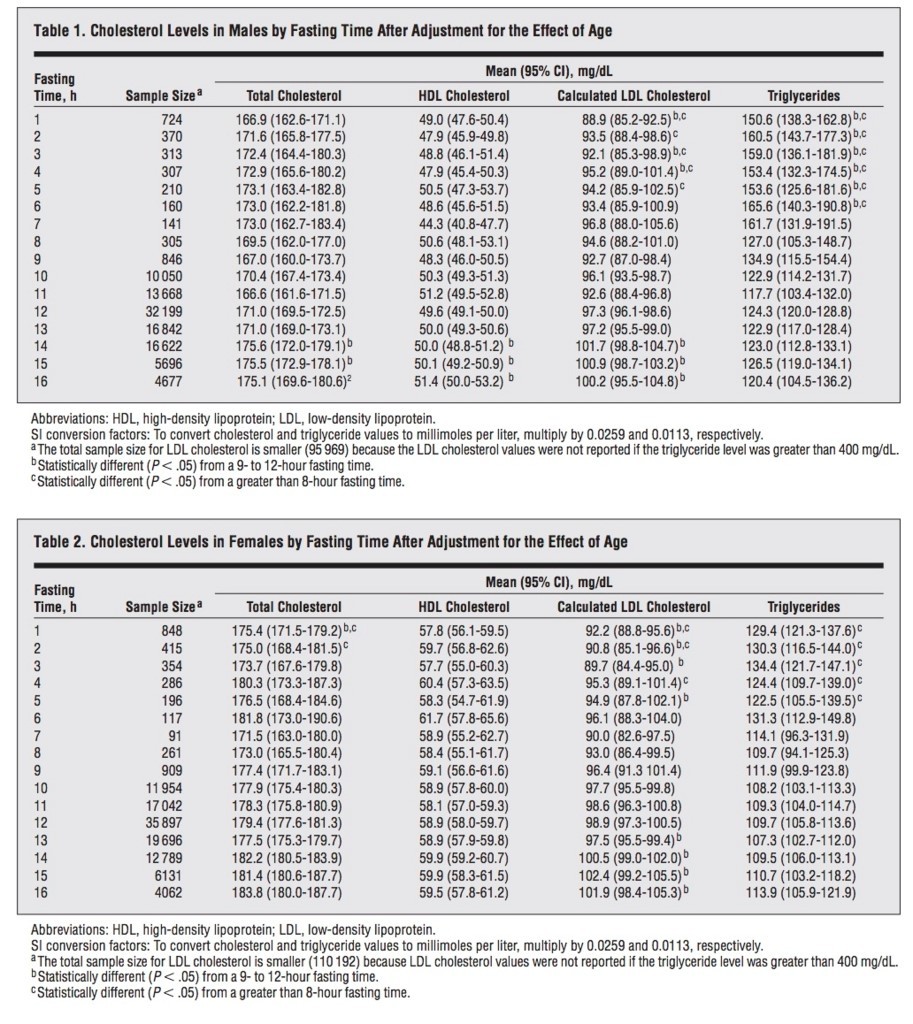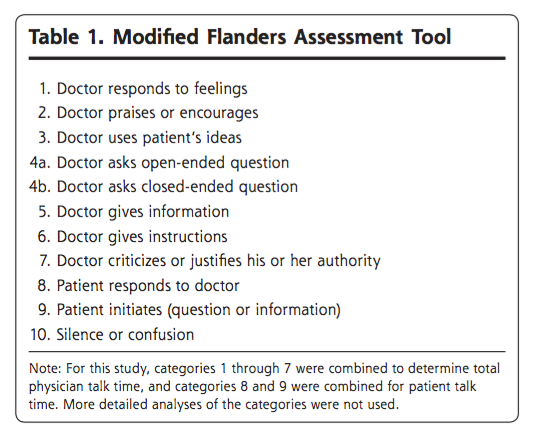-文献名-
Telio, S., Ajjawi, R., & Regehr, G. (2015). The “educational alliance” as a framework for reconceptualizing feedback in medical education. Academic Medicine, 90(5), 609-614.
-この文献を選んだ背景-
北海道家庭医療学センターではカリキュラム開発の枠組みとして5+1モデルを採用している。5つの構成要素については教育学の理論・研究に基づいてフェローへの教育や現場の実践が行われている一方で、+1の部分については家庭医療学の文脈から理解が主であり、教育学との関連が明確ではなかった。
この文献は+1の中の「学習者教育者関係」という部分について、教育学からはどのように捉えられているかを理解する助けになると思われたため、紹介したい。
-要約-
【医学教育分野におけるフィードバックの歴史】
フィードバックの重要性は幅広く認識されているが、フィードバックの実態や経験というのは十分に描写されてはいない。例えば、フィードバックへの受け止めには学習者側と教育者側で解離があるという研究が多くある。更には、フィードバックを行いさえすればよいわけではなく、状況によっては不利益に繋がることもわかってきた。そこで、良い・悪いフィードバックの特徴が研究され、結果として文脈を考慮していない、「唯一解」(Best practice)的な、処方箋的な推奨がなされてきた(PNPのようなサンドイッチやPendleton rulesはその例である)。しかしそれでも思ったような成果は出ていない。
【フィードバックにおける枠組みを拡げる】
このようにうまくいかないのは、医学教育分野においてフィードバックを「教育者が情報を届ける・学習者に受け入れてもらう」と捉えすぎる余り、何を言うか・どうやって言うか、ばかりが推奨され、それを受け取る学習者や、それを取り巻く関係性・コンテクストが無視されてきたからという視点が広がってきている。実際にいくつもの研究から、学習者がフィードバック行った人をどう理解しているか、学習者と教育者の関係性、学習者が判断するフィードバックの信憑性が、フィードバックの受け止めに影響していることが示されてきた。しかし、フィードバックにおける関係構築やコンテクストへの理解・探索を深めるための理論的枠組みはまだ提示されていない。この点について、心理療法の分野での研究が、分析や探索を進めてくれる可能性がある。その中でも治療的関係、という概念をここでは理解のための枠組みとして提案したい。
【心理療法における治療的関係’Therapeutic alliance’の考え方とその有用性】
実はこうした理解の変遷は心理療法の分野での変遷と似ている。つまり、治療者が患者に情報を与えるという枠組みから、関係性へと視点が移ってきた。Greensonは、患者が治療者と共に変わっていこうとする能力を強調する為に、’Working alliance’という言葉を作り、Bordinが1治療者と患者の相互理解、2目標や課題に向かうための方法についての合意、3患者の治療者への好み・信頼の3つの要素がその中にあると提唱した。この言葉が受け入れられるにつれ、Therapeutic allianceと呼ばれるようになった。
後の研究では、治療的関係は治療者の解釈よりも患者の解釈が重要であることや、心理療法の方法よりも治療的関係が心理療法の結果により影響することが示されてきた。
【治療的関係を教育的関係に置き換える】
治療者患者関係と教育者学習者関係は、変化を促す為のフィードバックの提供という点において非常に類似していると言える。よって、上記の心理療法における知見で捉え直すことで、教育におけるフィードバックも捉え直すことが可能である。例えば、以下のようなことが示唆される。
・治療的関係においては、治療者の認識よりも患者の認識の方が重要である。よって、教育者学習者関係も学習者の視点からの判断が重要となる。
・フィードバックプロセスも学習者の目標とパフォーマンスに対する共通の理解基盤の構築、アクションプランの合意形成、目標に向けた共同作業の実践と捉えることが可能である。
・フィードバックの「方法」(PNPや5microskillsなどのようなもの)も、唯一解(best practice)的な「踏むべきステップ」と捉えるのではなく、効率的な教育的関係を構築し、維持する為に利用できる、(しかも複数の中から選択できる)道具にすぎない、と捉えるべきである。
・FDにおいてもこの枠組みに乗っ取るのなら、フィードバックを学習者の実践を変えるためのものではなく、教育的関係の構築の道具として伝える形になりうる。
・更には、教育的関係の枠組みを踏まえると、効果的なフィードバックを行うためには、いざフィードバックを行う時だけに着目するのは不十分だということが示唆される。学習者は、教育者について情報収集と解釈を積極的に行っており、教育者が学習プロセスにどのようにコミットしているのかを初対面の時から考えていると捉えられる。
【限界と今後の方向性】
もちろんこういった治療者患者関係が医学教育に当てはまらない部分もある。(関係性の長さや境界線の保ち方など)
また、ここで述べたことの多くは推論にしか過ぎず、答えというよりは新たな問いを生み出すものであるが、今後の研究によって更に理解を深められる可能性がある。
-考察とディスカッション-
5+1モデルという形では学習者との関係性を意識していると、この文献で述べられていることの一部は自分の実践とも合致しており、納得感があるものであった。その一方で、中には、関係性の構築の視点を踏まえることで、フィードバックや指導医養成がどう変わるかについてははっとさせられる内容もあった。そういった意味では、我々が日常臨床で使い慣れた枠組みを教育へ丁寧に適用することで、教育実践に対する新たな理解・研究の視点が得られる好例だと思われた。更には、家庭医療学は医師患者関係についての枠組みを豊富に持っており、それを適用したリサーチを行うことで、この分野への貢献も可能だと思われた。
【ディスカッションポイント】
<学習者教育者関係について>
1.これまで関わった学習者を思い出して、その学習者とはどのような関係性を構築していたでしょうか?
自由に述べて頂いても構いませんし、家庭医療における医師患者関係の枠組みを参考に振り返って頂いても構いません。
(例:パターナリスティック-決断の共有の関係-消費者主義)
<フィードバックについて>
2.医学教育において、唯一解的なフィードバックの方法論を教えることがしばしばありますが、そういった手法は教育的関係にどのような影響を
与えていると思いますか?皆さんの実体験を元に振り返ってみて下さい。
例:批判のサンドイッチ、5micro skill、SNAPPSなど
【開催日】
2016年10月19日(水)