-文献名-
Franko, J. P. How to Lead Up in Your Organization. Family Practice Management, 2017, 24.6: 6-9.
-要約-
多くの医師は勤務医であり,大きな組織の中で何らかの役割を担っている。
「Leading Up」とは、Michael Useemの著書にある概念で、組織の中の(特に直属の)上司が行う意思決定に影響を及ぼす能力のことを指す。上司のリーダーシップに不安や不満を持つことは往々にしてある。なぜなら彼らはリーダーシップだけで今の立場に立っているわけではないから。上司の欠点を指摘するのは簡単だが、たいてい有効・健全ではない。代わりに、7つのスキルを用いて自分たちのリーダーシップを高めることで組織に良い影響をもたらすことができる。
1. Develop emotional intelligence(EI)
天性のものもあるが、EIは努力して高めることができる。EIとは、自分と他者の感情をモニターし、感情の違いを認識し、適切にラベリングし、思考や行動に応用することの能力である。特に自分の感情をモニターすることは重要である。感情のままに突っ走ってしまうと大抵問題が起こる。感情的反応を抑制するためにはself-awarenessを高めることが大事で、どんな時に自分の感情のボタンが押されるのかを知っておくとよい。そして、反応が起こりそうな時には「停止ボタン」を押す。例えば、深呼吸をする、唇をタップする、他の人に「もっと教えて」と言う、など。
2. Use power and politics for good
「power:権力」や「politics:決まりごと」は良くも悪くも組織内の関係性に影響を与える。個々人のもつpower、politics、関係性を正確に評価する必要がある。
3. Choose being effective over being right
医師は、正しくあろうとする特徴がある。しかしこれが組織への影響力を弱めることがある。「正しいこと」を証明しようとして多くの争いが起こっている。勝った方は満足するが、人間関係は悪化する。正しさと影響力を天秤にかけて考える必要がある。また、「正しいこと」の基準は人によって異なる。意見の相違に直面したときは、論争を始めるのではなく、体を向けて好奇心を持ち、他者の見方と価値観を理解するための質問をしていく。それによって、問題よりも関係性を重要視していることが伝わり、事態を収束に向かわせる。こういうことを行っていると、上司からは「bridge builder」や「positive cintributor」として見られることになる。
4. Be intentional and prepared
組織内での影響力を増すには、心の中のゴールを意識し目的を持って自分の言葉や感情を用いることが大事である。また会議やプレゼンの前には十分に準備をする。
5. Help your supervisor
まずは上司のauthorityとpowerのリミットを理解する。上司の意思決定能力や指示能力を過剰評価することは珍しくはない。上司はしばしば様々な制限を受けているのだが、それに気づかずフラストレーションを溜めてしまうことがある。次に、上司のニーズとゴールを理解する。そして自分の問題を上司目線で捉えてみる。上司を飛ばしてさらに上司にアプローチするのはやめたほうがいい。
6. Disagree without being disagreeable(感じよく反対する)
聞き飽きた表現かもしれないが、win-winの解決策を探ることは重要である。コモングラウンドが見つからない場合、無理して結論を出さずに意見の違いを認め合うのがよい。また、人を避難するのではなく物事を問題と捉えるよう心がける。
7. Don’t expect credit
自分のアイデアが全員からの賞賛を得ることを期待するとうまくいかない。アイデアをシェアすることで蒔いた種は、上司や他のリーダーが取り込んだときのみ芽を出す。そしてしばしば上司やチームのアイデアとして示される。そんなときは自分の手柄にこだわるのではなく、アイデアが走り出したことを幸せに感じるのがよい。
【開催日】2017年12月6日(水)
-1024x639.jpg)
-1024x553.jpg)
-1024x784.jpg)
-1024x530.jpg)




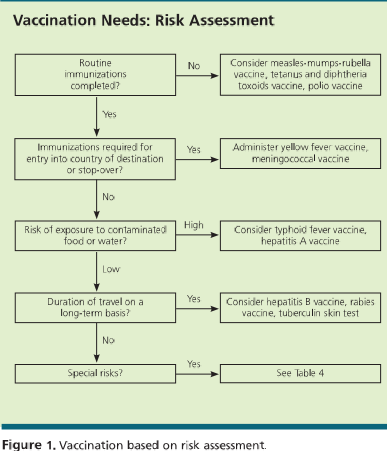
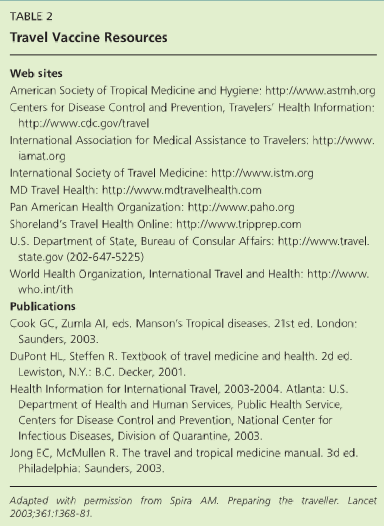
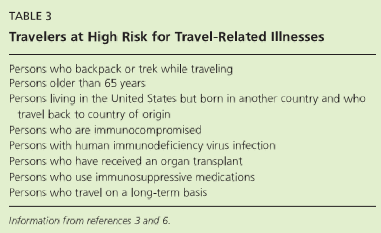
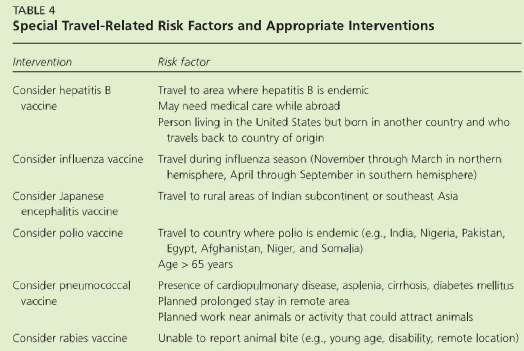
.jpg)
.jpg)




