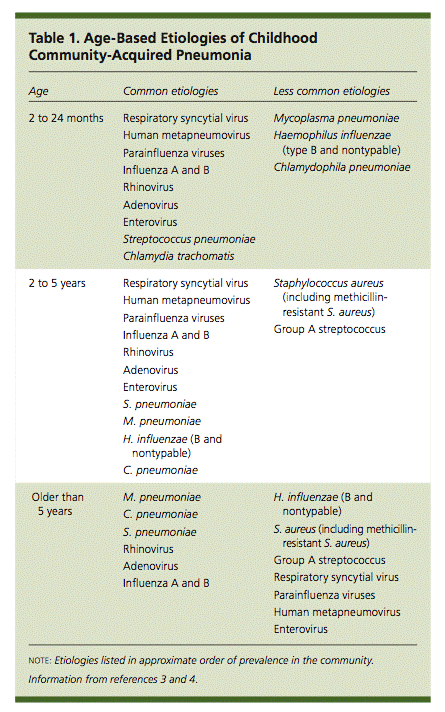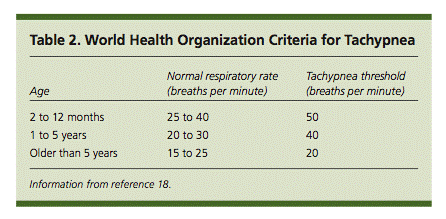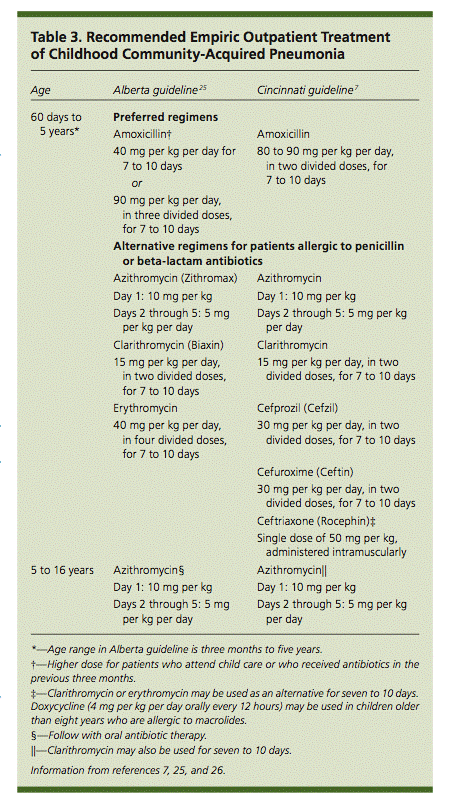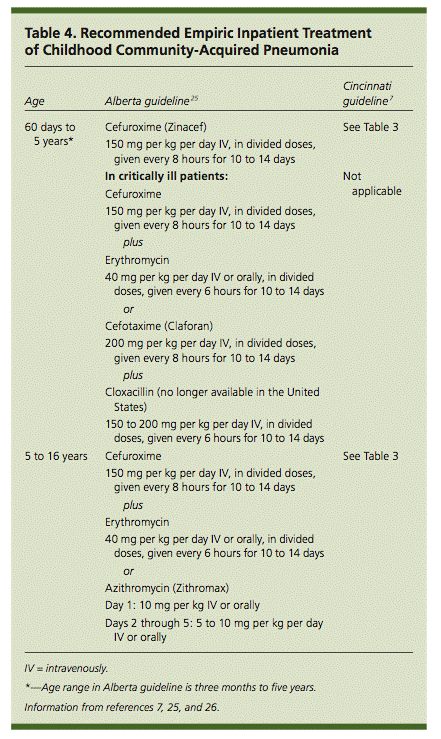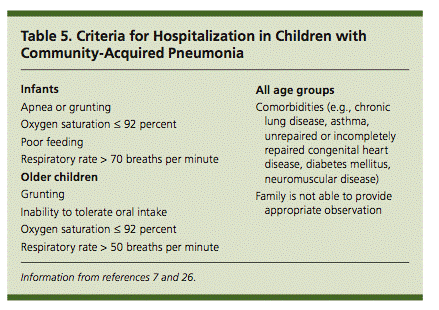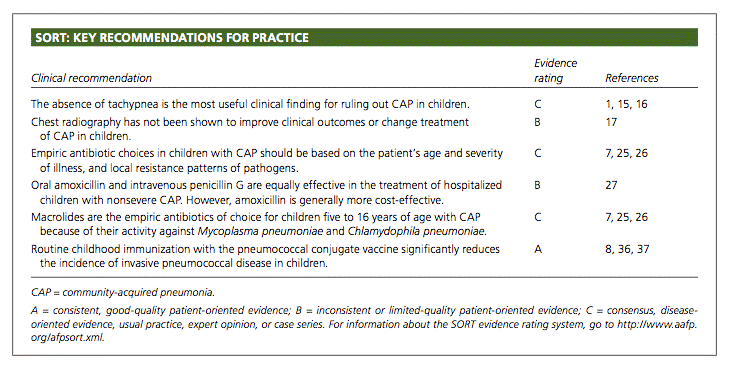【文献名】
Stucky Schrock K, Hayes BL, George CM. Community-Acquired Pneumonia in Children. American Family Physician 86(7), p661-p667, 2012.
-要約-
【病因】
2歳未満の小児ではウイルスが原因の大半を占め、年齢と共に比率が減っていく(Table1.)。小児では市中肺炎の30%~50%がウイルスと細菌の混合感染である。細菌性の市中肺炎では肺炎球菌の頻度が最も高いが、ワクチンが広く接種されるようになり重症の感染症の発生率は低下した。学齢期の市中肺炎ではMycoplasma pneumoniae、chlamydophila pneumoniae,肺炎球菌が主要な原因である。
重症事例ではブドウ球菌、とくにMRSAが原因として増えつつある。ブドウ球菌は特異的な所見がみられないため診断はチャレンジングである。 重症例や直近にインフルエンザ感染を伴う例、βラクタムやマクロライド系抗菌薬が奏功しない場合には疑うべきである。
【診断】 市中肺炎の臨床診断では第1印象が重要である。数ある肺炎を示唆する所見の中でも頻呼吸がもっとも重要なサインであり、正確に計測するために患児が静かにしている状態で、1分間フルでカウントすることが望ましい。発熱している児において頻呼吸のない場合は高い陰性的中率(97.4%)を誇る。 反対に、陽性的中率は低い(20.1%)。頻呼吸を呈している発熱児の場合、陥没呼吸や呻吟(grunting)、鼻翼呼吸、捻髪音の存在が肺炎の可能性を高くする。WHOは発展途上国でX線が利用できない環境では頻呼吸を診断の指標としている(Table 2)。 胸部レントゲン写真が診断としてよく用いられるが、陽性所見は臨床上のアウトカムや治療方針を大きく変えることにはつながらない。画像検査は診断が病歴や身体所見で診断がハッキリしないときや矛盾する結果が得られたときに有用である。画像所見で細菌性肺炎を疑うことが出来るが、特異的な所見はない。CRPやプロカルシトニン、血沈は細菌性の肺炎の診断に有用ではない。喀痰培養は採取すること難しく診断や治療のためには限定的にしか利用できない。血液培養はマネジメントを変化させることはなく、起因菌を明らかに出来ないことが多い。
【抗菌薬による治療】 市中肺炎診断時の最初の抗菌薬の選択は経験的とならざるを得ない(Table3,4)。 抗菌薬の選択は患者の年齢、疾患の重症度、よくみられる起因菌の薬剤耐性の地域性を元に判断する。 経口投与が難しいか、重度の市中肺炎でなければ抗菌薬は経口投与が望ましい。重症ではない市中肺炎の入院症例では経口のアモキシシリンとペニシリンGの経静脈投与はほぼ同等の効果を示し、費用対効果に優れたという研究がある。
治療期間 適切な治療期間はRCTにより確立されていない。多くの場合、外来における経験的治療の場合7日~10日間の治療で十分である。アジスロマイシンは5日間継続すべきである。経験的治療を開始した24~48時間後には再評価を行うべきである。経験的治療で効果がない場合、抗菌薬の選択が不適切であったか、初回投与の抗菌薬に対する耐性か、合併症の発症である可能性がある。
【対症療法】 発熱、胸痛、腹部への放散痛、頭痛、関節痛などを訴えることがある。アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛薬を用いる。アスピリンはRye症候群のリスクがあるため用いない。
【入院治療】 小児から思春期の肺炎の入院決定は臨床的、社会的、多様な要因で決定される。4か月未満の乳児はウイルス性またはChlamydia trachomatis感染を疑う場合か無症状でこまめなフォローアップが可能でない限り原則として入院である(Table5)。
【予防】 いくつかのガイドラインが市中肺炎予防のための方法を紹介している。 頻繁な手洗い、タバコを避けること、母乳栄養の推奨、他の児童との不必要な接触を少なくすること、予防接種である。13価の肺炎球菌ワクチンが認可されている。その他インフルエンザワクチン、Hibワクチン、百日咳、水痘、麻疹ワクチンの接種が推奨される。
【開催日】
2012年11月14日