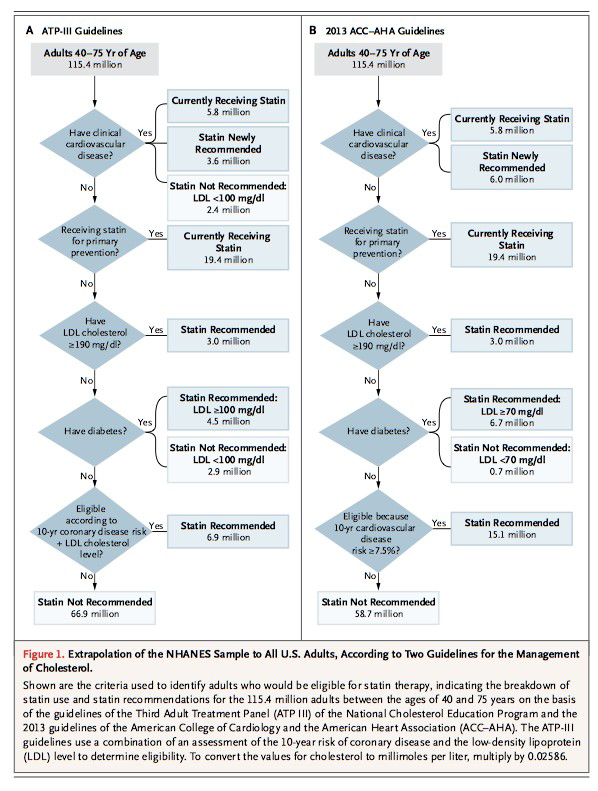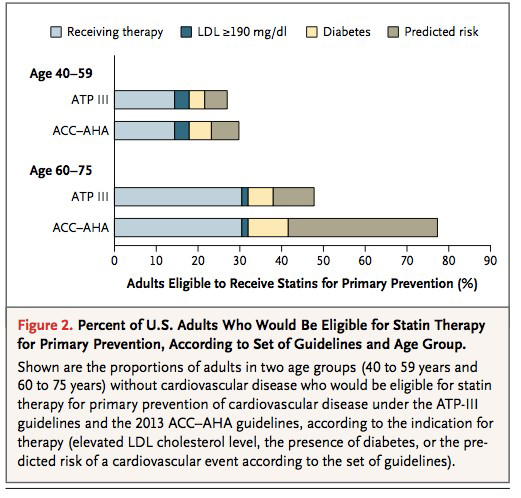―文献名―
「知ってるつもりのリハビリテーションの常識非常識」 三輪書店 2009年 安保雅博、橋本圭司 編著
―要約―
連携・教育における常識非常識 より抜粋
1.リハビリテーション医から
1 リハビリテーション科医の視点
リハ医の治療目標は、目の前の患者を、その方が到達しうる最も高い生活機能レベルに、いかに早く到達させるかにある。そのためには専門科目の枠を超えて、全ての医学知識と医療技術が動員されなければならない。一方、原因疾患の治療で消耗した患者は、自ら起き上がる気力に欠けており、主治医の積極的な声かけが必要である。これはリハ医や療法士がいなくても、主治医が決意し実行すれば簡単にできることである。リハビリテーションの始まりは主治医自ら働きかけることであり、その効果は患者さんのより速い回復として実感することができる。
3.作業療法士から
1 連携に必要とされる基本的能力は「振り分け能力」である
予防医療も含め近年の医療は急速に高度化・専門分化している。福祉制度も目まぐるしく変更されている。このような現状の中で利用者(患者)は、どの専門職が何を専門とするか知らない、どんなサービスがあるか知らない、どのサービスを利用すればよいかわからない、時には問題を抱えていることすら気がつかず悩む、そして一人で悩み、極端な場合には発見さえされない。利用者自らが昨今の変化を理解し、うまく利用していくことは困難なのである。利用者の立場に立ち、利用者の視点から問題を把握し、適切な専門職に依頼していくこと、つまりは「振り分け能力」を有していることが連携するときに各専門職に要求される基本的能力であるといえる。
2 連携の出発点は各職種間の「相互理解」である
上述したように、連携のために各専門職に必要とされる基本的能力は「振り分け能力」であるといえる。その前提となるのは、各専門職がお互いの職務内容を熟知していることであるが、果たして他職種の職務内容を十分に理解し、把握しているだろか。あるいは、他職種に自らの専門性や職務内容を知らせる努力をしているだろうか。この一見すれば当然と思われる事項が効果的な連携を進めるときの出発点であるといえる。
5.心理士から
3 よりよいカウンセリングのあり方
患者が問題に直面し、解決の糸口を見出しかねている時、問題解決へのさまざまな可能性をスタッフと共に考え、共に探ることをカウンセリング過程という。カウンセリング過程を遂行する際には、次のような基本的態度が大切である。
1)患者をあるがままに受け止める(受容する)
患者の言動が一見理解しがたくても、患者にとってはそれは一番バランスのとれる行動であることが多い。スタッフは、患者の訴えを退けたり、諭したりせず、そのまま受け止めることが大切である。なぜなら、患者は自分の訴えを受け入れてもらえないと、気持ちの一歩が踏み出せないからである。スタッフの接し方によっては、患者の不安を増幅させることも多いので、その影響を理解し、患者に対する接し方を振り返る必要がある。
2)共感する心をもって接する(共感する)
「共感する」とは、患者の問題を患者の立場から理解すること、温かい支持的態度をとること、相手の立場を理解したということを伝えることである。患者は「自分のことをわかってくれる」「気持ちが通じる」と感じると、訴えは少しずつ軽減する。この場合、患者の言動に振り回されず、「症状の背景にある患者の気持ち」を考えながら、余裕のある対応が大切である。
3)患者自身の負う責任をスタッフが引き受けない
患者は自分で問題を解決する能力を持っている。スタッフが指示したり、価値観を押し付けたりすると、患者自らが解決するチャンスを奪ってしまうことになる。また、家族への援助についても、患者を理解するための知識や情報の提供、実生活での援助活動は大切なことであるが、家族の関係性から生じている問題への安易な介入は避けるべきである。
―考察とディスカッション―
これまで家庭医として勉強する中で触れてきたことや、普段の診療の中で何となく気付いていたことが言語化されており、しかもそれが様々な職種の視点で記載されていることが印象的だった。他職種が、それぞれどのような考え方で動いて専門性を発揮しているのか、またそれぞれの職種が「他の職種のスタッフにも知っておいてほしい」と感じていることは何なのか、といったことの理解に繋がると思われた。今回紹介した部分以外はもっと各論的なものも多く、読み物としてお勧めしたい書籍だと思う。
【開催日】
2014年6月11日(水)